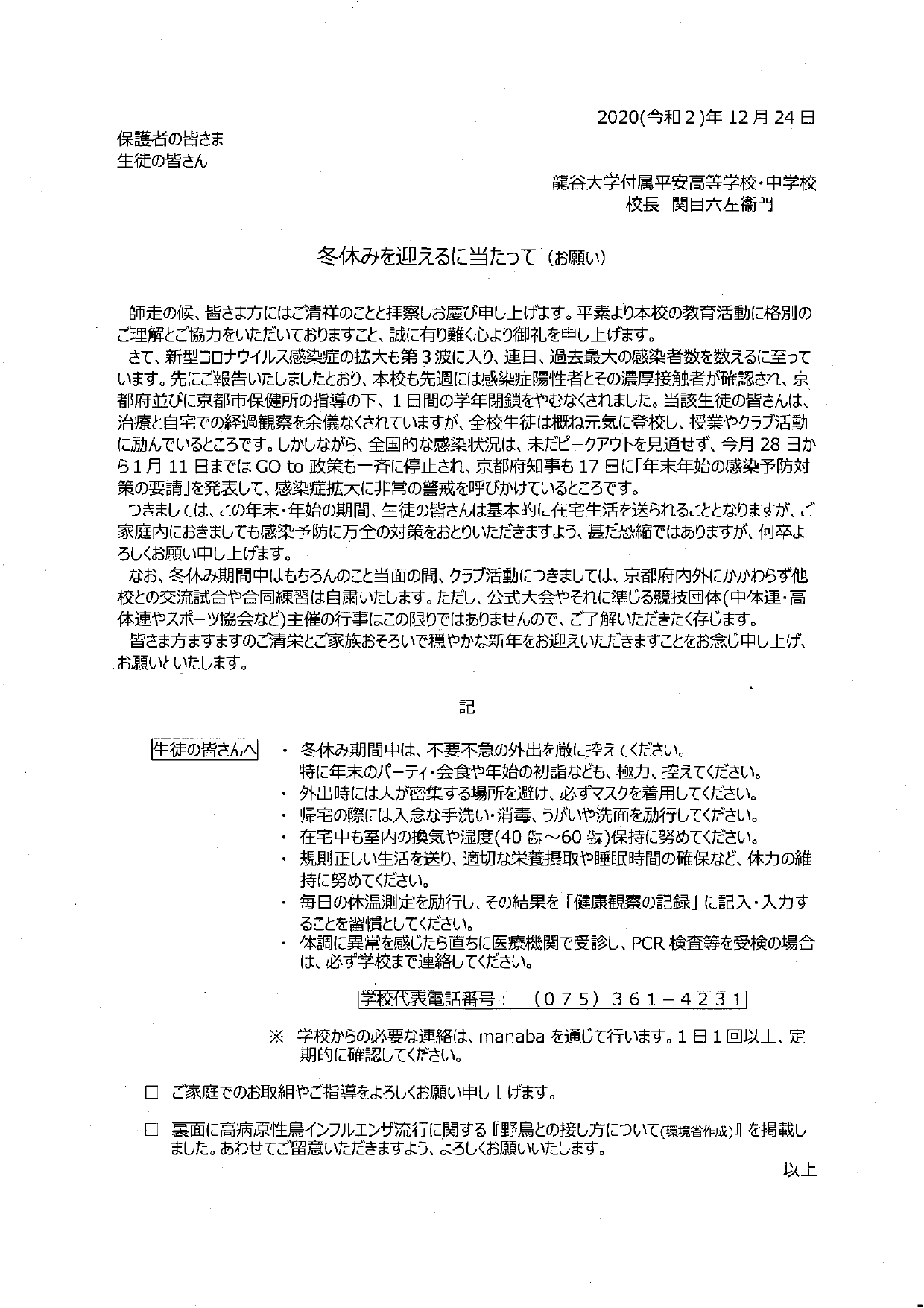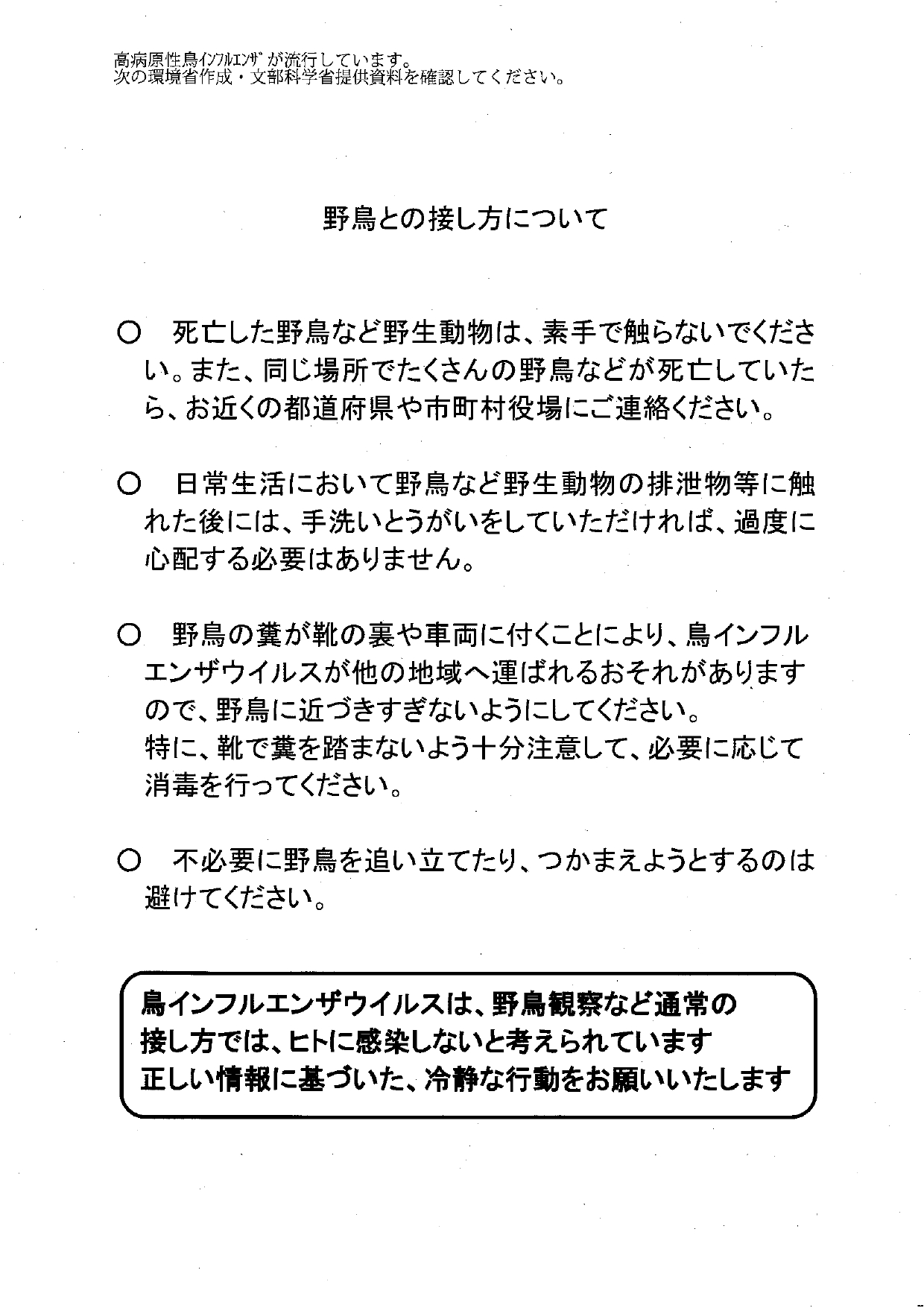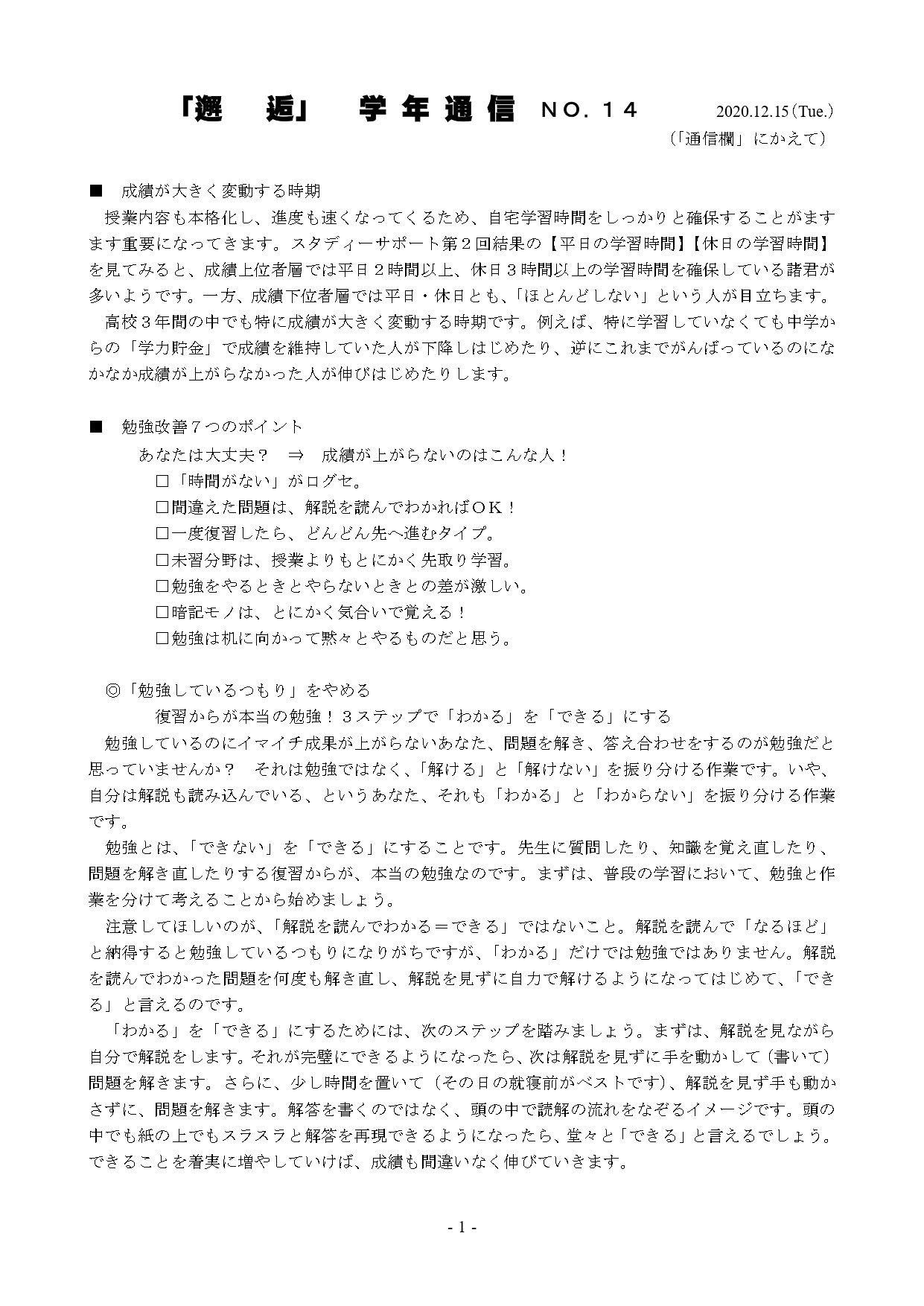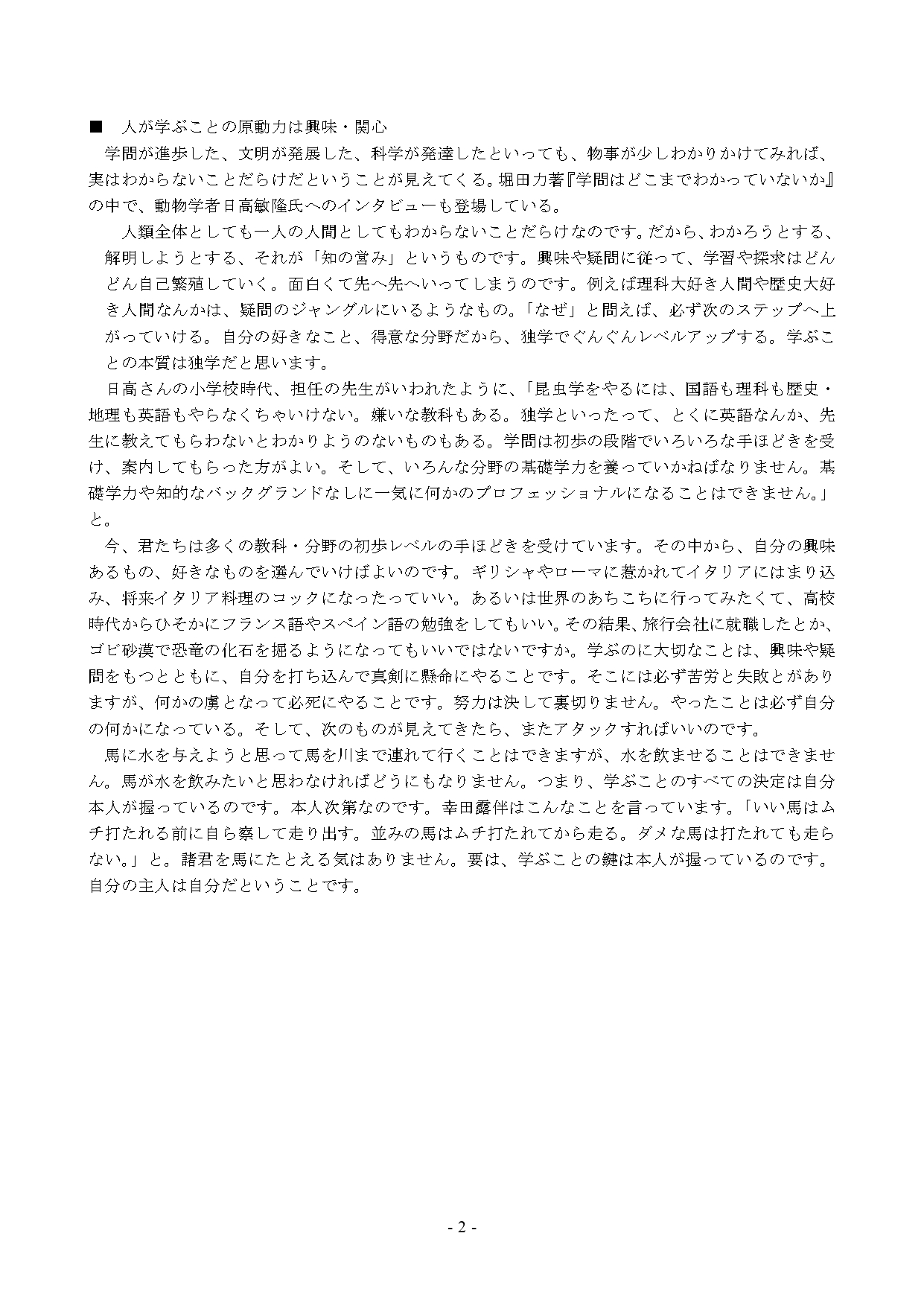本日の仏参は10組担任の山下先生のお話でした。
山下先生は、今までに約20ヵ国に旅行され、様々なものをご自身の目で直接見て来られました。当時はインターネットが今ほど普及しておらず、海外の情報も少ない中で、言葉が通じない世界に強い関心を持たれたそうです。今回の仏参では、海外旅行を通して経験されたこと、そこで感じたことをお話しされました。
言葉の通じない異国の地で、メニューがないレストランや移動手段としてのバスの乗車、観光地でのマナーなど様々な場面で困ったことがありましたが、現地の人が優しく教えてくれたそうです。見ず知らずの日本人に優しく接してくれたことから、普段忘れかけている優しさに改めて気づかれたそうです。そこで山下先生は「ありがとう」という感謝の言葉を現地の言語で伝えるように心がけたそうです。
最後に山下先生自身の考えとして、「いただきます」「ごちそうさまでした」という食前・食後の言葉が示すように、日本の文化は感謝を伝える文化ではないかとお話しされました。日々の生活の中で感謝の言葉を伝えることを大切にと締め括られました。
私たちの日常を振り返ると、多くの人の支えや応援・励ましがあって成り立っています。改めて今ここに生かされているということを自覚し、その感謝の気持ちを言葉で伝えることを大切にしていきたいですね。