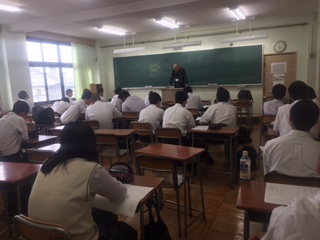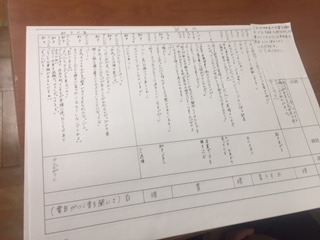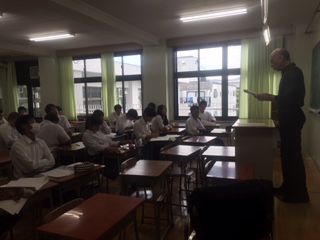本日は第6回目の高2仏参日でした。
ブレザー着用が不要となり、筆者の位置からではきちんとした仏参に臨む姿勢ができているのかわかりにくくなりました。
ですが、遅刻者の数は少ないようなので、多くの生徒がきちっとできているように見えます。(本日遅刻者席にきたのは1名でした)
本日の御法話は4組担任の中森先生から頂きました。
まず、昨年のお話に触れられました。
昨年中森先生は「人生の選択肢」について語られています。
人生の中では様々な選択をする場面があります。
高校受験しかり、大学受験しかり、就職しかり。
しかし、どのような選択をしたとしても、選択した先でどのような人生を送るかこそが最も重要であること。
戦国時代の武将 武田信玄の『一生懸命なら知恵が出る、中途半端なら愚痴が出る、いい加減ならいいわけが出る』という言葉のように、愚痴やいいわけのようなマイナスのものではなく、知恵のようなプラスのものをだせるくらい、一生懸命に過ごすことを伝えられたそうです。
さて、今年のお話は一生懸命にやっていても認められない、誰もわかってくれないと感じてしまう。
厳しい言葉を掛けられてしまうことがあると言うお話です。
今回のお話の主題は“自分の身の回りには自分を見守ってくれて、支えてくれている人が居る”というものです。
一生懸命でありながら、周りから厳しい態度で接せられるということは、自分のことを見てくれているということ、支えてくれているということです。ですが、なかなかそれに気付くことはできません。
中森先生は学生時代にずっと軟式野球をしておられました。
大学に入って野球を始める際に大学のレベルの高さに驚かれましたが、ここで結果を出して頑張っていこうと奮起されました。
1回生のときは試合経験が無いまま2回生となり、春のリーグ戦ではレギュラーで試合に出ることが出来るようになったそうです。
しかし、レギュラーになられるまでに、「他のメンバ-を追い抜かすつもりでやらんと試合には出れん」「お前のポジションを取ったるぞ」などといった厳しい言葉をキャプテンから掛けられ続けていたそうです。
「なぜ自分だけこんなことを言われるのか。」そういった不満が募りつつも、小さい頃からの夢である“全国制覇”に向かってリーグ戦を戦い抜き、見事優勝することが出来ました。
自分の個人としての結果も上々で、頑張ってきた努力が報われたように感じられ、次の大会へ向けた士気も高まっていました。
ですが、その次の試合からメンバ-には選ばれなくなりました。
「他の戦力の強化のためか?」と初めは考えたそうですが、長くそれが続くようになり、また、キャプテンからも何も言われないようになって、どんどんと野球がつまらないと感じるようになっていったそうです。
「こんな状態では野球を続ける意味は無い。けじめとして大会中は部に残るけれど、これが終わったら退部しよう。」
そんな思いで続いた大会で、ついに敗戦したときに退部を告げにキャプテンへと会いにいこうとされました。
しかし、先にキャプテンに呼び出されてこのように言われたそうです。
「なぜ試合に使われなくなったかわかるか?俺はお前のことを弟のように思いながら見てきた。日頃のお前を見ていると、しっかりしてへんなぁというところが目について声を掛けていたけれど、ここしばらくは甘やかしてばかりでいたらあかんなぁと思って、何も言わなかった」
言われてすぐにはその言葉をすんなりと受け入れらたわけではなかったそうですが、思い返すとリーグ優勝で満足して、その後満足にヒットが打てなくなったり、いいかげんにしているところがあったと気付いたそうです。
それから、今までの自分の考えが自分の都合ばかりになっていて周りのことを全く考えていない自己中心的な考えであったとわかったそうです。
そうして、その一言から、自分のあり方を悔い改めて最後まで野球をやり通すことができたそうです。
大抵の人は自分にとって良い話、物事は欲しますが、嫌なことからは耳をふさいで聞こうとしない、逃げてしまいがちです。
自分にとって周りが厳しくなって自分ばかりが責められているように感じるのなら、まず自分の行いを見直してみることが必要です。
自分に対して厳しく接する人は、それだけ自分の先に期待していることにつながります。良くなって欲しいとの願いがあります。
自分の考え方が傲慢になっていないか、自己中心的な考えに陥っていないかよく考えて、誰かに言われる前から自分の振る舞いを是正できるように日々を過ごしてもらいたいと思います。