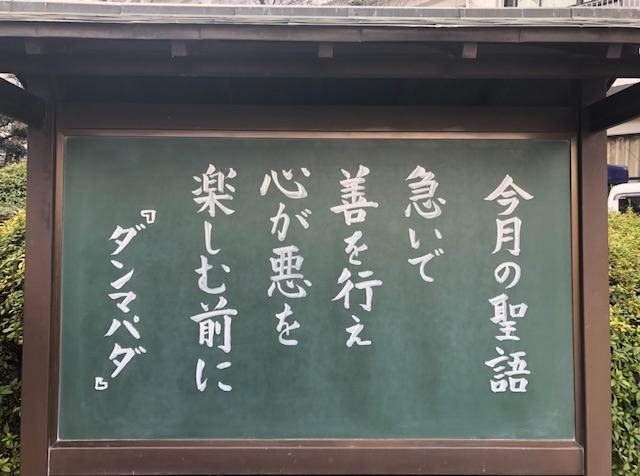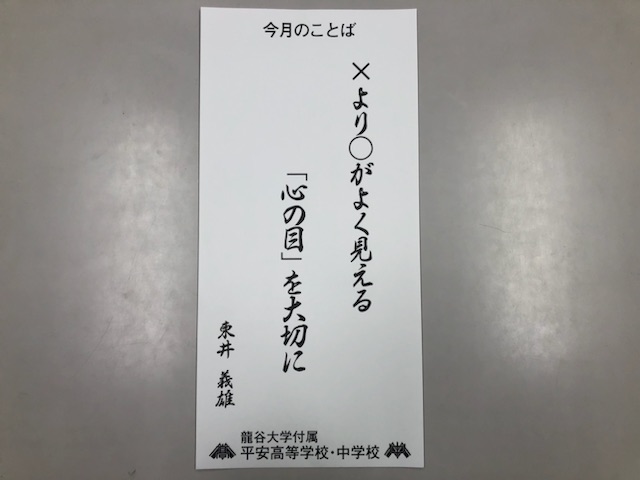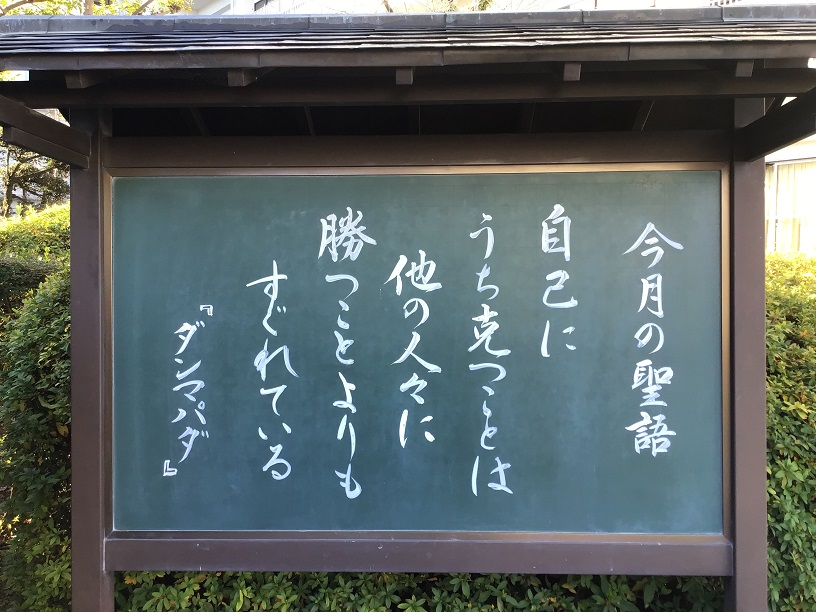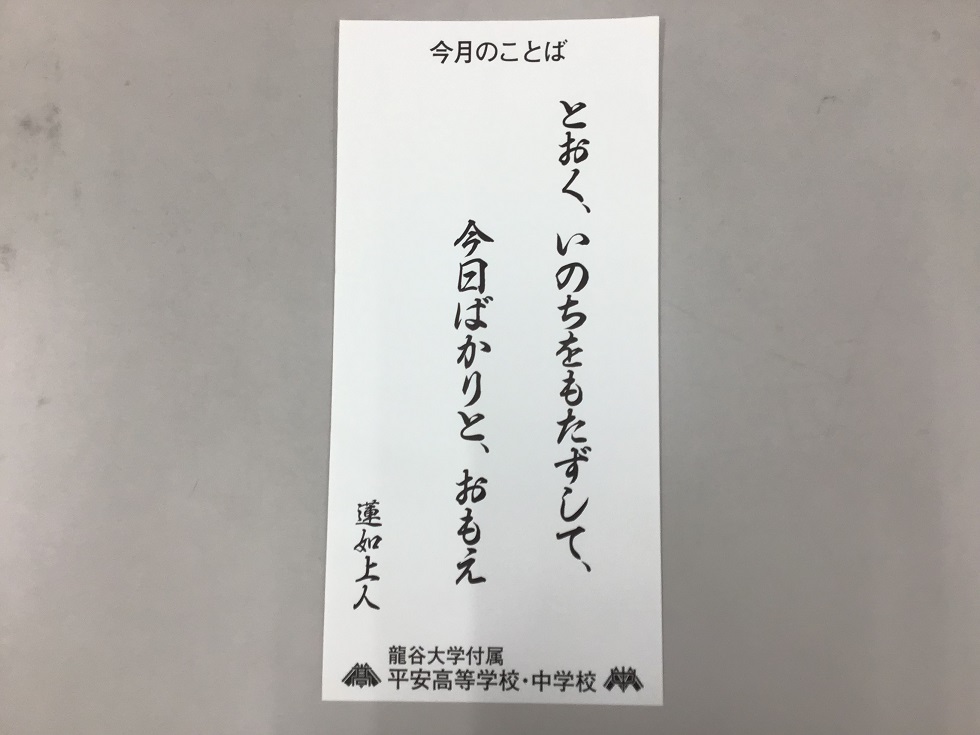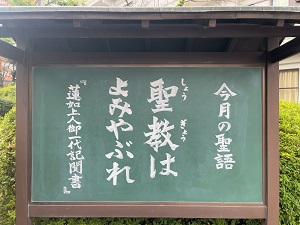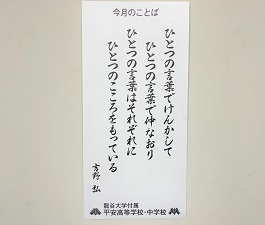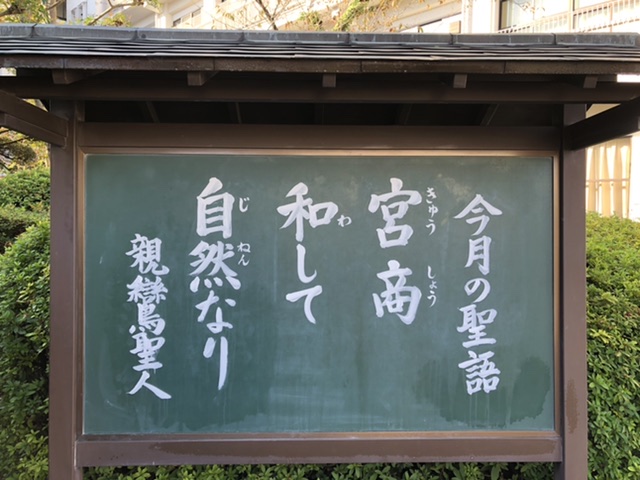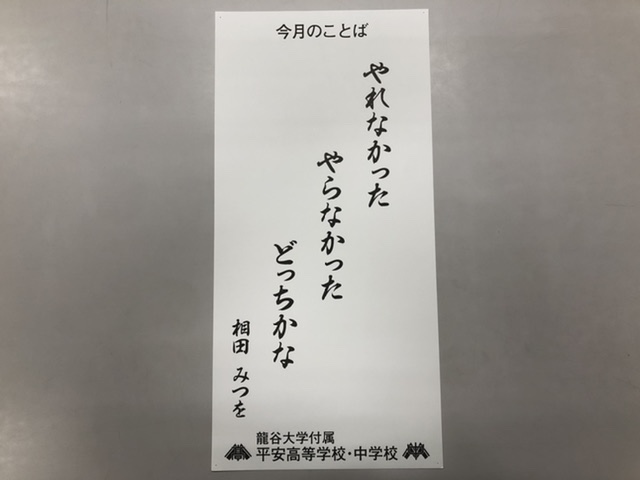本日10時から涅槃会をお勤めしました。昨年と一昨年はオンライン配信でしたので、ようやく講堂でのリアル涅槃会となりました。
ご講師は、浄土真宗本願寺派布教使の藤澤彰祐(しょうゆう)先生でした。藤澤先生は子どもの頃から「醤油」と人にからかわれ、ご自身の名前を嫌いだったそうです。しかし、大人になって「お念仏のみ教えを大事にしていってほしい」という願いが込められていることに知り、その名前の奥に込められた願いにったときに、ご自身の名前を好きになったと言います。そして、「これが出会い直しというものだ」とおっしゃいました。
次に、お釈迦さまと阿弥陀さまの違いについてお話されました。お釈迦さまは2500年前にインドでお生まれになった方ですが、阿弥陀さまは人間の体をもってお生まれになった方ではありません。
お釈迦さまは亡くなられたのではなく、さとりとして私たちを導き、仏法に出遇えるようにご縁を結んでくれている。心の目を見開いたときに出遇える究極のさとりの世界に入っていかえれたことから「涅槃に入られた」と言い、お釈迦さまがさとりの心の目で出遇っていかれたのが阿弥陀さまなのです。そして、お釈迦さまは「自分の人生の意味もいのちの意味も、阿弥陀様に出遇わないと出遇えないよ」と私たちに説いてくださったのです。そして、藤澤先生は「仏さまの心に出遇うということが、本当の自分に出遇うということ」だと示されました。
最後に、お釈迦さまの弟子の一人であったシュローナのエピソードをお話されました。自分の足で歩く必要すらなかったお金持ちのシュローナは、お釈迦さまの弟子となります。しかし、歩くことがなったシュローナは托鉢にまわることすらままならず、教団を去ろうとします。それを見たお釈迦さまは、ヴィーナ(弦を弾いて演奏するインドの發弦楽器)の名手だったシュローナに対し、ヴィーナの弦を通して「人や過去、理想の自分と比べず、あなたにとってできることを精一杯やりなさい」と諭したのでした。そのお言葉に触れたシュローナは、教団を去ることをやめ、いのち終えるまで自分の精一杯の努力をされたのでした。このシュローナと自分を重ねたとき、生徒たちはいろいろ考えせられたのではないでしょうか。