1月14日火曜日 欠席者なし 記入者:2年
明けましておめでとうございます(遅くなりました)。今年もよろしくお願いします。新年初めての部活でした。今年の目標をみんなで話しあい、気を引き締めました。また、それぞれ各自のレポートと展示室のリニューアルについて去年と同様に行いました。
新入生に来てもらえるように日々精進していきます。
1月14日火曜日 欠席者なし 記入者:2年
明けましておめでとうございます(遅くなりました)。今年もよろしくお願いします。新年初めての部活でした。今年の目標をみんなで話しあい、気を引き締めました。また、それぞれ各自のレポートと展示室のリニューアルについて去年と同様に行いました。
新入生に来てもらえるように日々精進していきます。
日誌 2025年12月19日(木)
参加者:全員 記入者:2年生
今日は2024年最後の考古学部の部活動でした。主な作業は、部誌作成のための各自での調べ事とそのまとめとなるレポートの作成と、考古学展示室に陳列されている須恵器をはじめとする考古遺物の、より分かりやすい解説文(キャプション)の作成作業でした。普段はにぎやかな部室ですが、今日は各々自身のテーマに沿った調べ学習や展示されている遺物の詳細な観察を黙々と行いました。また6月に出かけた春季遠足の概要をまとめる作業も行い、改めて春の見学を振り返ることができました。
来年も、引きつづき部誌・展示室リニューアルなど、考古学部の活動に精を出していきたいと思います。
考古学部 日誌
12月17日火曜日 参加者:全員 記入者:1年生
本日の内容
自動的に生成された説明 今回は、第8回考古学写真甲子園に応募する写真を選考しました。それぞれが自分の撮った古墳を見せ合い、一番良いものを選出しました。部員ごとに個性があり、また、どの写真にも味がありました。そのおかげで、特別な1枚を選ぶのに苦労しました。
今回取り上げている写真は、ある部員が撮ってきたものの一つです。左の小さな丘が古墳だそうです。秋晴れの中に滑り台と古墳。風情のある良い写真です。
*前回の記事の答え
前回の記事に合った埴輪は「鹿形埴輪」でした。鹿が見返りをうっている様子が埴輪になっています。
考古学部日誌
出席者:全員 記入者:2年
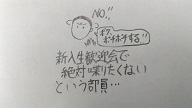
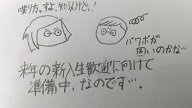
今日は部活の今後の方針を定めました。具体的には、
紀要(年報)制作に向け、各部員が執筆するテーマの決定
考古学展示室内の須恵器を効果的に活用する方法
の2つです。まず①の紀要は、部員増加のための広報を強化する、また今行っている活動を未来に残すという目標のもと、年度ごとの発行を予定しています(名前はお楽しみに!)。そこで、各部員が各々興味のある「モノ」の歴史に関するレポートをまとめることになっています。「モノ」を中心にするのは、考古学が「モノ」から歴史を紐解く学問だからで、加えて部室に隣接する展示室の考古遺物の有効活用にも繋がります。また②で挙げた「須恵器」も、わが部が誇る収蔵品のひとつです。須恵器とは、古墳時代に伝えられた土器の一種で、灰色がかった色調などが特徴的な硬質の土器です。考古学部の先輩方はその須恵器の窯跡の発掘に参加し、そして数多くの遺物を部に残されました。その先輩たちの努力・成果を受け継ぎ、活用し、未来に伝えるためにも、須恵器の有効活用の方法を考案していくことが大切だと感じます。

12月3日火曜日 参加者:全員 記入者:1年
本日の内容
本日は、石橋先生に飛鳥宮跡で発見された天武天皇の内裏正殿(だったのではないかと言われている建物)についてのお話をして頂きました。飛鳥宮跡の調査で見つかった掘立柱建物跡の中で、これまで一番大きいものはエビノコ郭にあった大極殿跡でした。しかし、今回の調査でそれよりも大きい掘立柱建物跡が見つかったのです。それが、天武天皇の内裏正殿だと考えられているそうですよ。(根拠は→一番外側の柱の間隔が他と比べて広い点が平城京の内裏と共通している/発見された建物の規模からするに、天皇の内裏であると考えられる)
飛鳥宮、と聞いても自分の知識不足もあり、良くも悪くもぱっとした印象がありませんでしたが、今回のお話を聴いて、また一つ知識を増やすことができました。今後も、活動の中で飛鳥宮跡の知識について深めていこうと思います。
考古学日誌 11月14日
欠席者なし 記入者 2年
今日は日中にテストがあったため、みんな疲れを感じながら活動しました。平城宮跡の見学を終えて、それぞれが担当する平城宮跡のスポットをレポートにまとめました。期末考査の終了後、みんなで確認していきます。
考古学部日誌
11月12日(火) メンバー4人 欠席1人 記入者2年
本日の内容
各自で平城宮跡で学んだことのまとめを先生に添削してもらい修正した。自習も行い、有意義な時間を過ごした。先生の添削はわかりやすく、プラスで知識を増やすこともできた。また明後日に控えているN検の対策方法も教えてくださったので、いつもより時間が経つのが早かった気がする。