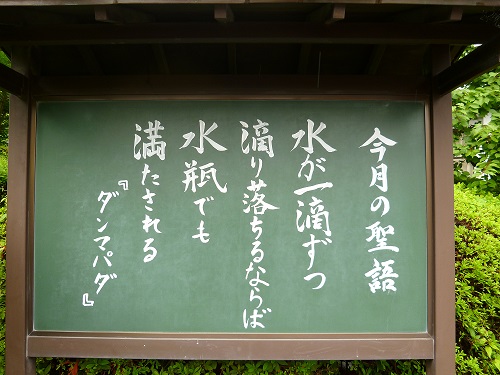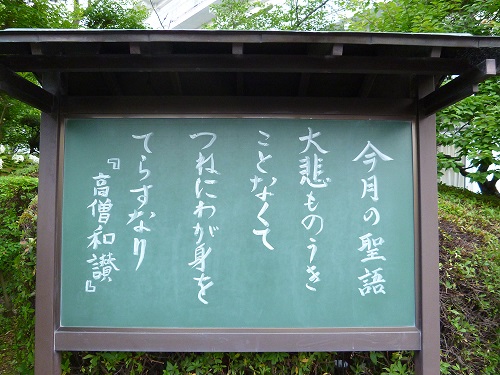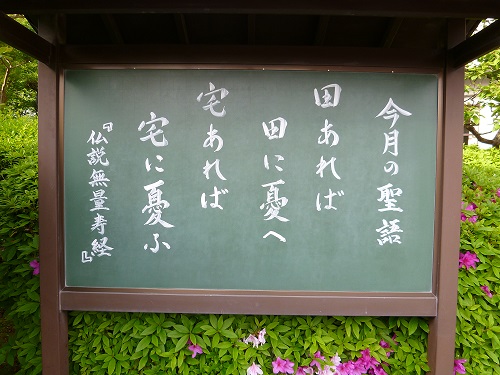7月20日(火)は,今月最後のお稽古でした。
短縮授業期間のため,お昼をいただいたあとすぐに稽古を始めました。
外は大変な猛暑ですが,カフェテリアの中も暑く,少し辛い中で一生懸命稽古に取り組んでくれました。
欠席者・早退者が多く人数が限られていたため,割り稽古やお茶を点てる練習は省き全員が畳の上でお点前を見る形をとりました。
最後に,2グループに分かれてお通いの練習をしました。お茶を運び,お出しするという一見簡単そうな所作も,実際にやってみると難しいことがわかります。前の人とのタイミングをはかったり位置を調整したりしていると,そちらに気を取られてお茶をこぼしそうになってしまい…(実際には空のお茶碗で練習しています!)
人数が減り少し寂しい部分もありましたが,そのかわり全員お点前をすることができ充実した稽古になったのではないでしょうか。
ちなみに本日のお菓子は壬生の鶴屋鶴寿庵さんの「屯所餅」でした。
残念ながら文化祭での茶会は行えませんが,茶道部独自の茶会を必ずどこかで実施したいと思います。それまでしっかり稽古を重ねていきましょう。